先行まちびらきから見えてきた、新たな可能性
-グラングリーン大阪南館開業後の変化と、まちの発展に向けた兆し-
2025.10.09 Thu

世界有数の大規模ターミナル・JR大阪駅前に誕生したグラングリーン大阪。
北館やうめきた公園の先行まちびらき、そしてJR大阪駅直結の南館の開業を経て、この場所は今、どのような場として機能し、まちにどのような変化をもたらしているのか。
本記事では、グラングリーン大阪を中心としたまちの今とこれからの展望を、プロジェクトに参画したメンバーの視点で綴ります。
INDEX
この1年の変化と、まちの今の様子
「まちでの出会いが、さまざまな価値を創造し、持続的にみんなと社会全体を良くしていく。」※
そんな想いのもと誕生したグラングリーン大阪は、2024年9月に北館やうめきた公園が先行まちびらきし、続く2025年3月には南館が開業。これまでの梅田にはなかった、広大な「みどり」を中心とした都市空間が生まれ、まちの風景を大きく変えるとともに、人々の関心を惹きつけています。
北館に隣接する芝生エリアは、店舗と一体化した憩いの場として日常に根づいています。加えて、南館の開業により、回遊性やエリア全体の魅力も向上。
公園と施設がシームレスにつながることで、世代を問わず来街者が自由に過ごせる空間となり、「日常と非日常が交わる場所」という、まち自体のコンセプトが体現されています。
※グラングリーン大阪 開発コンセプト
https://umekita.com/concept/index.html

北館「Bean There, UMEDA キャノピーbyヒルトン大阪梅田」前

南館内
さらに、南館内のホテル「ホテル阪急グランレスパイア大阪」「ウォルドーフ・アストリア大阪」の開業や、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の影響もあり、海外からの来街者も増加。国際色豊かな風景が日常となりつつあります。
来街者の顔ぶれも時間帯で大きく異なり、早朝は近隣で暮らす方々が散歩や静かな時間を過ごす場として訪れ、日中は商業施設利用者やオフィス就業者、ファミリー層、夜には若者やカップルの姿も。都市にある公園としてさまざまな利用が定着し、人々の日常に確実に浸透しています。
各エリアの使われ方と思いがけない広がり
先行まちびらき以降、うめきた公園を中心にさまざまなイベントが開催され、公園の新しい使われ方や想定を超える反響が生まれています。
2025年5月には、「MIDORI FES. 2025 ~公園から『世界にいいこと』に取り組む文化祭~」※1を開催。
環境課題をテーマに据え、空に浮かぶ「雲バルーン」やステージイベント、ワークショップなど、誰もが楽しめる仕掛けが話題を呼び、グラングリーン大阪全体で延べ80万人が来場。「雲バルーン」は、来街者が"明日を楽しくするアイデア"をカードに書いて託す参加型の企画で、空に浮かぶメッセージが公園全体を彩る象徴的な演出となりました。
これまで環境分野に接点のなかった層にも広がりを見せ、反響は当初の見込みを大きく上回るものとなったことは、うれしい意味での想定外でした。

MIDORIFES.2025開催時の様子 サウスパーク前

続く6月には、茶屋町エリアで毎年実施されているイベント「100万人のキャンドルナイト」との連携による、世界中で開催されているコンサートシリーズである「CandlelightⓇ by Fever@うめきた公園」※2、そしてSuperflyによるカバーアルバム『Amazing』発売記念フリーライブ(ロートハートスクエアうめきた)※3 など、文化性・話題性のあるイベントを続けて実施。

キャンドルを囲んで演奏に耳を傾ける来街者の様子

Superflyによるカバーアルバム『Amazing』発売記念フリーライブ(ロートハートスクエアうめきた)には約2万3千人が集まり、「ターミナル駅前でこの規模のイベントができるのは梅田だけ」とSNSでも話題に。都市の中でこれほど大規模かつ多様なイベントが日常的に開かれる風景は、予想以上の広がりでした。

Superflyによるフリーライブ開催時の様子

撮影:渡邉一生 / SLOT PHOTOGRAPHIC, ハヤシマコ
こうした大型イベントに加えて、2024年9月の「YOSETE UMEKITA」(寄席をテーマに現代と伝統のカルチャーを交えた屋外パフォーマンス)※4や、2025年1月に実施された「いきもの調査」(京都大学発スタートアップと連携)など、文化・学術・エンターテインメントが交差する催しも継続的に行われており、さまざまな使われ方が定着し始めています。

桂九ノ一さんによる寄席の様子 撮影:倉科直弘(写真左)

生き物を探して記録する様子
特に「いきもの調査」は、都市の中心にある公園で生き物の存在に目を向けるきっかけをつくるもので、グラングリーン大阪が進める生き物の生息環境の整備や温熱環境の改善、緑地の質向上といった、自然との共生を目指す思想を来街者に伝える役割も担っています。※5
こうした多種多様な催しや賑わいを通じて、都市における公園の可能性や、まちが持つ発信力の大きさを、あらためて実感しています。
※1 MIDORI FES. 2025
https://umekita.com/ggo-special/midorifes2025/
※2 CandlelightⓇ by Fever@うめきた公園
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000125279.html
※3 Superflyカバーアルバム『Amazing』発売記念フリーライブ(ロートハートスクエアうめきた)
https://www.superfly-web.com/news/?id=8542
※4YOSETE UMEKITA
https://bench-p.com/projects/yoseteumekita2024/
※5 グラングリーン大阪における環境・生物多様性への取り組み
https://www.hhp.co.jp/news/2024/07/000660.html
梅田全体への影響

グラングリーン大阪の開業は、梅田のイメージを「買い物やオフィス街」から「くつろぎとゆとりのある空間」へと一新しました。エリア全体の来街者層が多様化し、JR大阪駅からグラングリーン大阪へと続く回遊動線が生まれ、梅田全体が「みどりと都市が融合する国際交流拠点」に進化する一歩となっています。
特に、前述のクラシック音楽をより幅広いお客様に気軽に楽しんでいただくことを目標としたパフォーマンス「Candlelight® by Fever@うめきた公園」では、茶屋町や西梅田といった周辺エリアで続けてきた取組が、公園を軸に連携し、広域的な動きへとつながりました。こうした"面で捉える"アプローチは、エリアマネジメントの視点から少しずつ積み重ねてきたもので、まちの価値を広げる流れとして定着しつつあります。
ウォーカブルな(居心地が良く歩きたくなる)まちづくりやパブリックスペースの活用の可能性も示す好例となり、都市の運営や企画に関わる関係各所の連携手法自体にも変化をもたらし始めています。
このようにグラングリーン大阪は、単なる都市公園ではなく、まち全体を育てていくための舞台装置として位置づけています。
こうした広がりの背景にあるのが、公園と民間開発を一体的に行い、公園整備後も50年にわたって民間が運営・管理を担うという、国内では例のない長期的かつ公共性の高い仕組みです。
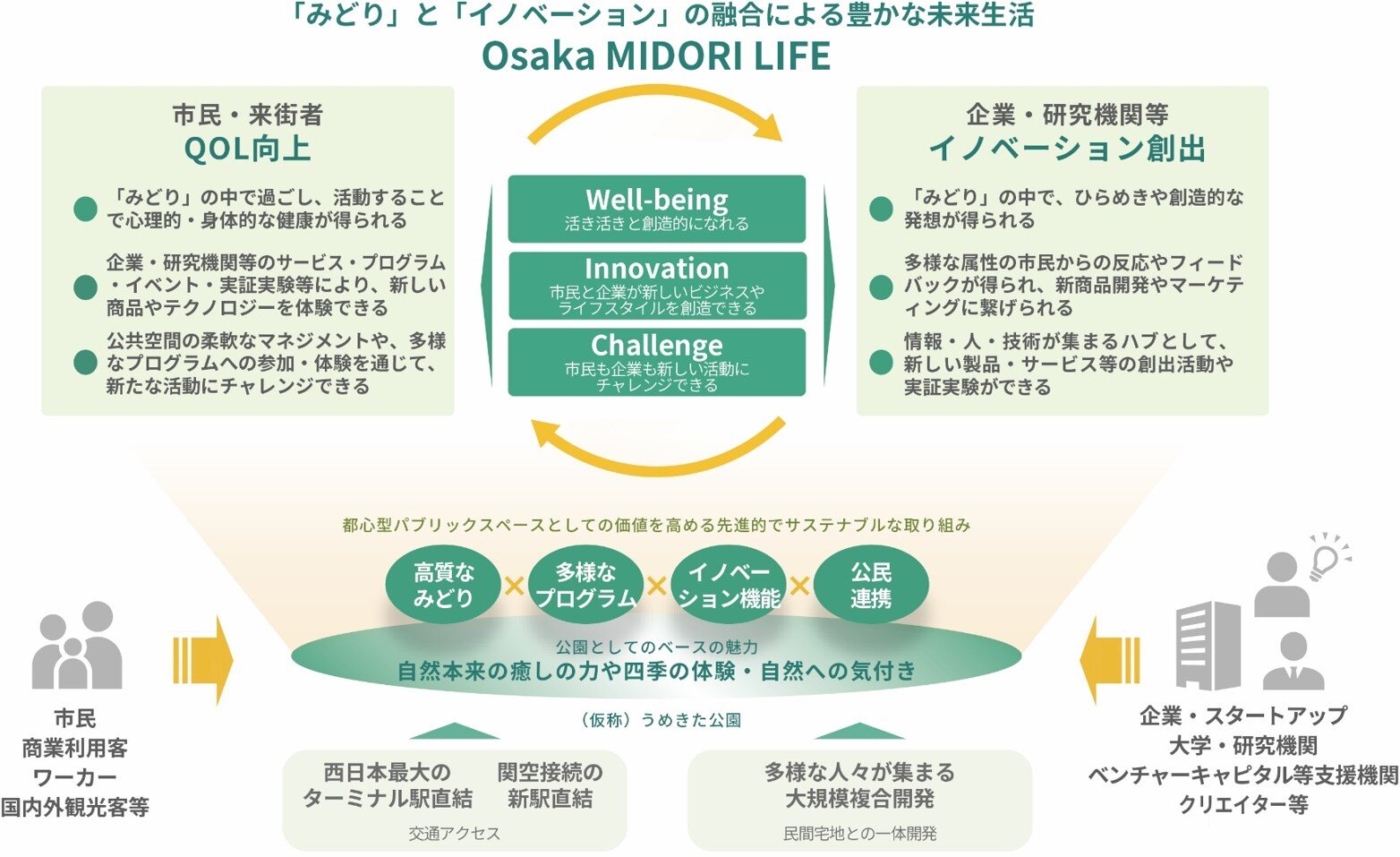
この先進的な都市運営モデルには、他都市のデベロッパーや自治体はもちろん、海外からも視察の依頼や問い合わせを多数受けており、エリアマネジメントの新しいスタンダードとして注目を集めています。梅田全体の魅力を引き上げ、持続的な都市の価値向上を目指すエリアマネジメント活動※においても、中心的な役割を果たし始めています。
※エリアマネジメント活動
都市の持続可能な発展をめざすため、官民一体となって、まちの魅力の向上に取り組むこと
これからの発展に向けて

グラングリーン大阪はこれから、まちのあり方をさらに進化させるフェーズへと入ります。
公園と周辺の施設がつながることで、訪れる人が空間を自由に行き来しながら、日常の中で自然と人や場との関係が生まれていく。そんな風景が、少しずつまちの中に根づき始めています。今後は、文化や環境、ビジネスなど、さまざまな領域が交わる都市空間としての可能性を、さらに広げていくことを目指しています。
その一歩として、「MIDORI CLUB」※など、市民がまちづくりに関われる新たな仕組みづくりも始まります。
訪れる人が、公園の環境保全やイベントの企画・運営に関わることで、まちの成長に自然と関わっていけるような場を育てていくーそんな取組が始まろうとしています。
実証実験やワークショップなども通じて、都市の中心で自分のアイデアや思いを形にできる機会が今後さらに増えていく見込みです。
2027年春頃には、北街区のノースパーク全面開園、2027年度にグラングリーン大阪は全体まちびらきを迎えます。
公園を軸にした都市の広がりがさらに加速し、梅田全体が"歩いて楽しいまち"としても進化していきます。
「みどりを都市の中心に置く」という挑戦のもと、人と自然、人と創造がつながり、日常が育まれていく。そんな"生きたまち"として、グラングリーン大阪はこれからも発展を続けていきます。
※MIDORI CLUB
公園を支え盛り上げる「まちのクラブ活動」として認定・サポートされる仕組み。誰もが参加できるオープンな活動を主体的に企画・運営できることを目指す。

